目次
節分はいつから始まった?
もともと節分は中国の行事。
奈良時代に日本に伝わり、平安時代には宮中の行事になりました。
室町時代に豆まきで鬼を追い払うという形になり、家庭に定着し、現代の節分となっています。
1年は春夏秋冬で分けられており、季節の変わりめは邪気が病気・火事・地震をはこんでくると考えられていました。
春夏秋冬、それぞれの季節の始まりは立春・立夏・立秋・立冬といわれています。
季節の変わり目の前日は邪気を払うための行事が行われていました。それが節分になります。
節分の漢字を見てみると「季節を分ける」となっていますね。

節分は何をする?
節分は「節目の日に邪気を払い、新年を幸多き年として迎えられるように」という意味を込めて平安時代には追儺と呼ばれる行事が行われていました。
追儺のひとつである豆打ちの名残が豆まきとなっています。
他にも鰯の頭を柊の枝にさして玄関先にたてる 、恵方巻を食べる、という風習があります。
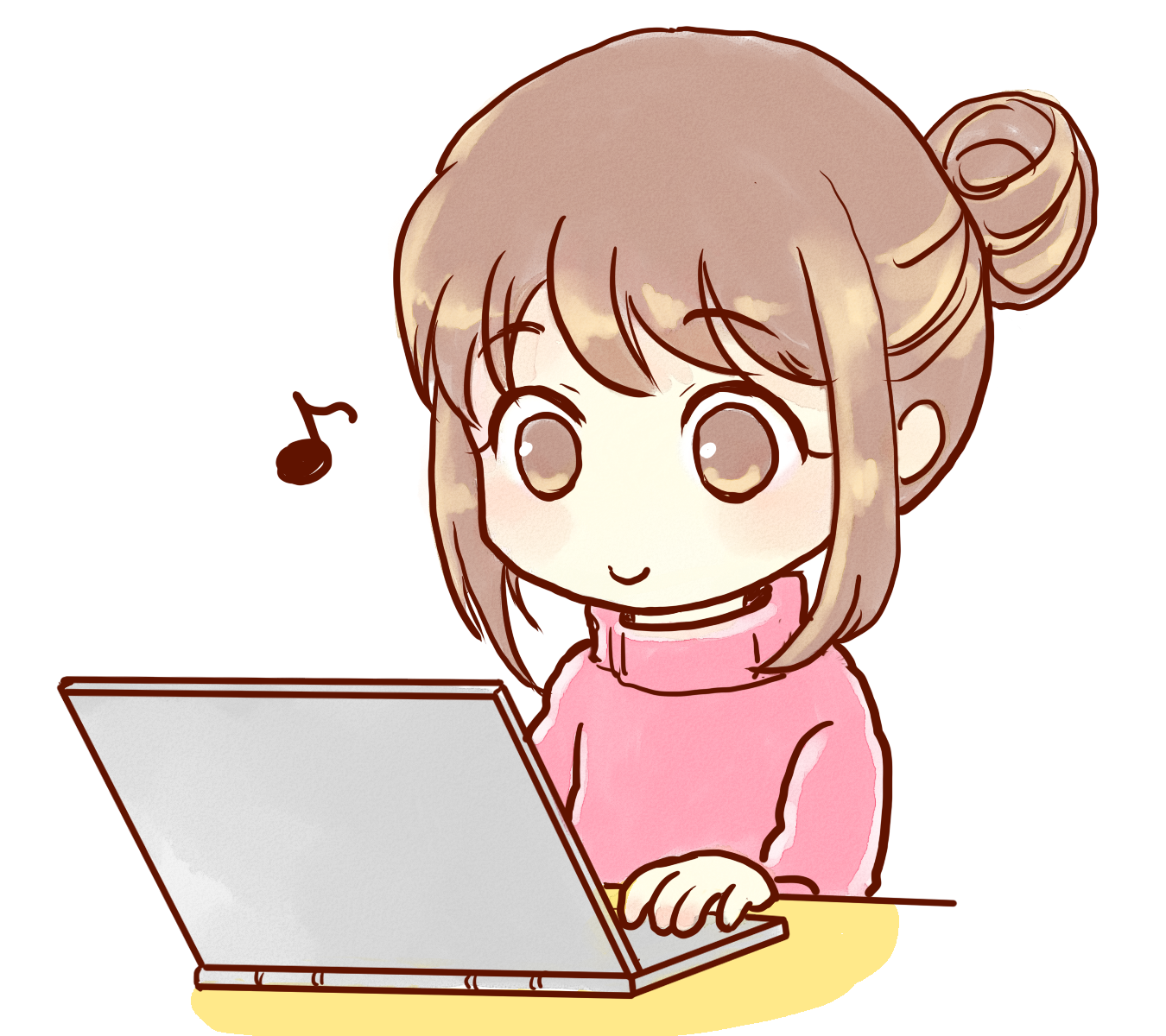 ひな
ひな次のページでは豆まきの由来、まく時間、いくつ食べるのか、恵方巻を柊鰯の由来を紹介します。








コメント